SWAMシリーズの記事も大詰めになってきました。
これまで表現の基本に必要なパラメータを扱ってきましたが、今回は音の質感に強く関わるパラメータをみていきます。
いくつかのステップに分け、管弦それぞれで整える方法をご紹介します。
別途EQプラグインを立ち上げて確認すると理解しやすいかと思われます。
2019.06.28
SWAMシリーズの記事も大詰めになってきました。
これまで表現の基本に必要なパラメータを扱ってきましたが、今回は音の質感に強く関わるパラメータをみていきます。
いくつかのステップに分け、管弦それぞれで整える方法をご紹介します。
別途EQプラグインを立ち上げて確認すると理解しやすいかと思われます。
☆Formant
フォルマント・・・EQをキャプチャした動画でいうと赤い線になっている部分のことですが、Formantパラメータを弄るとこのような音色の変化がおこります。
フォルマント:Wavダウンロード(約3MB)
フォルマント2:Wavダウンロード(約1MB)
音を口で真似していただくと分かりやすいかと思うのですが、母音でいうところの「u – o – a – e - i」の発音変化に似ています。
口腔内体積や口の形(アンブシュア)に合わせてフォルマントが変化するので、先ほどの例を奏者にも当てはめ、Formant [12.00~12.00]の範囲を[-12.00]u - o - a - e – i[12.00]の口の形と対応させて傾向を考えてみましょう。
例えば、吹き始めは-値を取り、吹き終わりに近づくにつれ+寄りになり、息継ぎがあれば若干-に戻し、ロングトーンなどを吹き切る場合は+にする…などが考えられます。
歌声ソフトにおける調声でも効果的で、歌詞の母音・子音・前後の口の形に合わせてフォルマントを変えると良い結果が得られます。
フォルマント一定だと、口の形を固定したまま発音しているような歌い方になります。
☆Harm. Struct
Formantが倍音構成をEQ的に変化させるものだとしたら、Harm. Structは比率を変化させるものだと考えると理解しやすいです。(Clarinetなどは特殊ですが…)
楽器によって設定できる範囲も異なりますが、基本的には低値であるほど基音が強調され丸みのある音に、高値であるほど倍音が強調され複雑な音になる傾向があります。
先述のFormantと組み合わせ、口腔内・口の形をイメージしながら変化させると理想の音色に近づくかと思います。
コントローラーに割り当てるならば、「噛む」動作が適当かなとも考えますが…如何せん他にも制御すべきパラメータも多いので難しいところですね。
ペダルなどを併用するのもひとつの手だと思います。
倍音構成を変化させるパラメータとして、OverBlow(倍音を強調するハーモニクス)Squeak(アタック音の裏返りや軋み)がありますが、これらは特殊奏法として考えます。ベロシティやエクスプレッションの影響も受けます。
☆Sub Harm
動画は440Hzを鳴らしている最中にSub Harmを上げ下げしたものです。
注目すべきは1オクターヴ下の音(220Hz)も鳴っていることです。
その他、整数次倍音の中間(660Hz)に影響することも確認できます。
音量は小さいですが、特殊効果として、スパイス的に用いると良さそうです。
澄んだ音色と深みのある音色を使い分けることができるようになります。
他に、優しめのGrowlの代用として使うこともできます。
GUIにもSub Harm > Growl > Flutter Tと横に並んでいるので分かりやすいです。
なお、Flutesにはこの項目は存在しません。
代わりにStyleというパラメータが存在し、Classic – Jazz – Funk - Ethnicとジャンルに合わせた音色デザインができるように工夫されています。
こちらは次にご説明するBreath Noiseの効きにも影響します。
全体的にノイズ成分が持ち上がりやすくなり、雑味が強くなります。
Flutesにのみ存在するパラメータとして、ほかにAltFがあります。
ある音域以上(楽器で異なる)にのみ作用し、特定の倍音以外の成分が大幅に抑えられます。
On/Offで制御するパラメータで、非常に澄んだ音が出せます。
☆Breath Noise
息による「ザー」とした分かりやすい雑味成分を付加できます。
変化はかなり複雑で速く、ザラザラ感を単純に重ねたような結果が得られます。
EQで見ると、先ほどのFormantやSub Harmで変動する山以外の部分(細かく振動している部分です)が持ち上がります。
息によるノイズはいつ発生しやすくなるか、大きく分けて2つ考えられます。
ひとつは、息が弱まり充分な共鳴が得られないとき。
もうひとつは、強く吹きすぎたとき。
つまり、吹き始めや吹き終わりなどのタイミングで変化させると良さそうです。
OverBlowやSqueakと組み合わせると、より複雑な表現ができます。
☆Breathy PPP
On/Offのパラメータで、高次の倍音を抑え柔らかな音色(特に弱音でブレスノイズが際立つ)になります。
切換時に若干ロードする時間が生じるので注意です。
この機能、現行版(2.8.4)のマニュアルには一応「ClarinetsとSaxophonesのみ」と書かれていますが、実は他の管楽器シリーズにもこっそり実装されています。
しかし、他のシリーズで適用してみると分かりますが、音色が掠れすぎて普通の設定では使えません。
CompressorやExpression Curveを併用するとまともに使えるようになります。
設定次第で尺八や篳篥、篠笛といった民族的な楽器をもデザインすることができます。
音色変化の基本は圧力の減衰と弦を弾く位置です。
「この音色にしたいからこの数値にする」ということではなく、「どのタイミングで不安定になる(力が変化する)のか」が大切だと考えています。
圧力が大きく変化するのは弓の返し前後、位置が大きく変化するのはその間です。
タイミングについて詳しくはVol.1の「ヒューマナイズの基本」、Vol.2の「運弓タイミング」を参照いただければと思います。
デモソング:Wavダウンロード(約3MB)
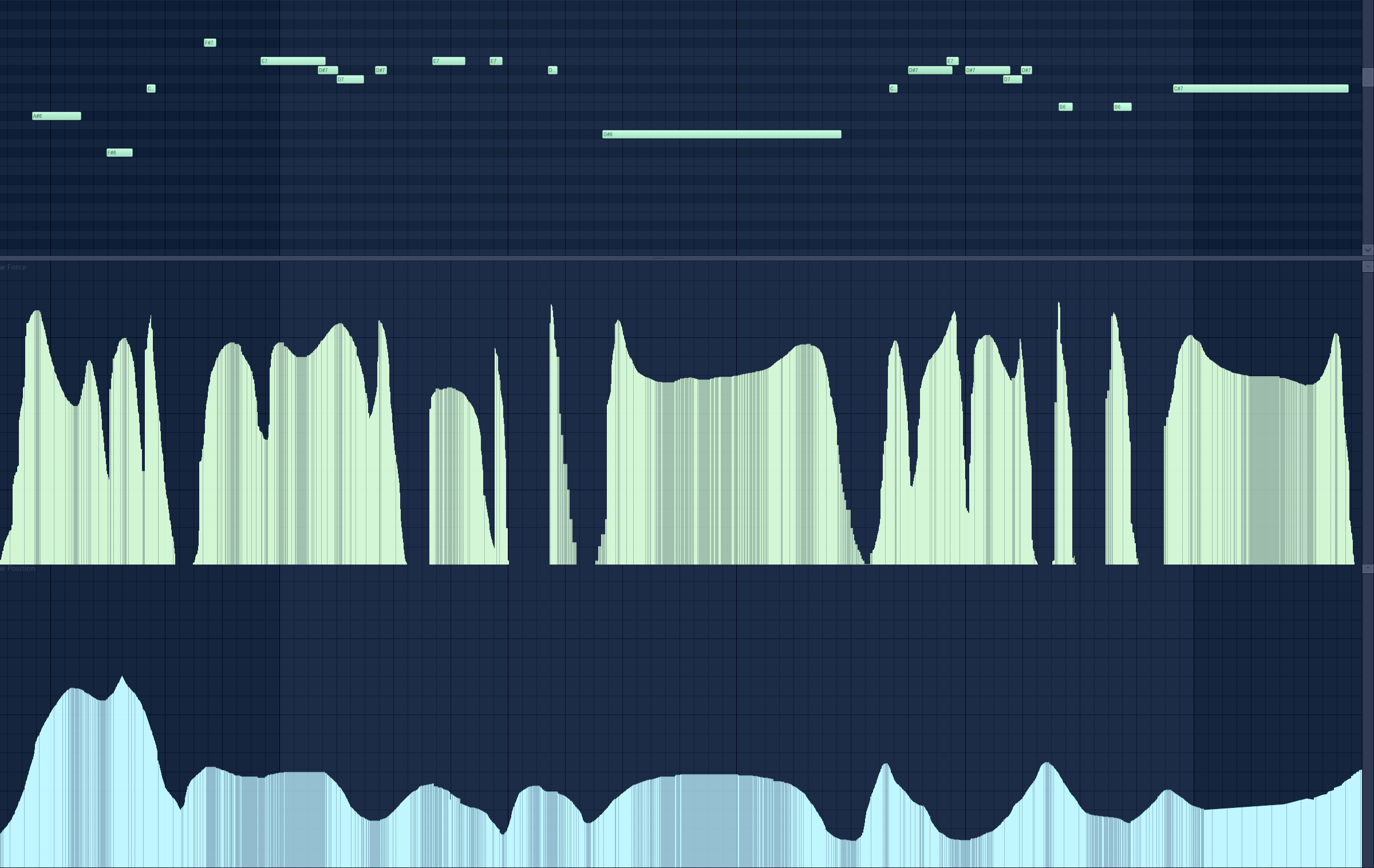
上が圧力、下が位置のグラフです。
複雑なグラフや、極端に逸脱した値を一瞬入れたりすれば更に表情豊かになるのですが、今回は傾向説明のために手描きでシンプルなグラフにしています。
しかしやはり手描きはかなりの労力を要しますので、弓の動きとリンクし感覚的に入力できる機器での入力をおすすめします。
私は弦の制御に関しては、現時点ではLeap Motionが最も優れていると思います。
木管楽器では成分を重ねたり倍音の構成を直接弄れたりと分かりやすかったのに対し、弦楽器では非常に難しいです。複数パラメータの組み合わせによって音色が変わるためです。
これらの組合せを知らないことには、中々思ったような音色にはなりません・・・。
更には
などの成分を別途適切に重ねる必要もあります。
パラメータの組み合わせは複雑で、言葉で説明するのが非常に難しいのですが・・・
傾向を考察するためにデータを取り、一覧にしてみました。
☆: 変化が認められるが微細なもの
- : 変化がほとんどないもの
○: Lift On
×: Lift Off
※名称を略しているパラメータもあります(Rnd: Random Bowなど)
これらはかなり限定的な音色ですが、傾向をみるのには役立ちます。
Bow PressureやBow Positionはもちろん、RosinやInteractive BPが摩擦の程度に大きな影響を及ぼすことがわかります。高圧力での濁りと音程のずれを補正したり、低圧力では倍音の変化をコントロールできます。
弓速が遅いと高圧力によって音程が非常に不安定になり、Bow Liftの影響も強く受けることがわかります。
Bow PressureやBow Positionできちんとヒューマナイズを施してから、他のパラメータでニュアンスの違いや安定性を崩すのが良いと思われます。
SWAMの特色として、「非常に整っている」ことが挙げられます。
これを崩すランダマイズ機能も搭載されてはいますが、変化が機械的ですからタイミングやさじ加減も考える必要があります。
この項では人間的な音程のブレに関わるパラメータをご紹介します。
☆Pitch Bend
SWAMではピッチベンドは一般的なものとは挙動が少し異なり、発音中の音を加工しているのでなくリアルタイムに生成しています。
弦楽器のGUIではピッチの変動によって指の位置が変わるので確認しやすいですね。
ピッチベンドによる音程変化では、開放弦の音程に到達しても移弦しません。
ピッチベンドのグラフだけでビブラート表現もできますし、奏法に限らず、基準のピッチを上げることで様々な楽器を模したデザインができるのも魅力です。
通常の音域を超えた演奏も可能です。
ヒューマナイズに関しては、次にご紹介するTemperamentの併用をおすすめします。
☆Temperament
Temperamentは楽器の演奏可能音域において、中央からの斥力・引力を設定するパラメータのように考えると良いかもしれません。
SWAM Violinの場合、最低音・最高音のちょうど間の音はF#4です。
F#4から遠ざかるほど、F#4に向けて音程が引っ張られたり離されたりします。
Temperament+では遠ざかり、-では引きつけられますが、中央であるF#4はどのような値を設定しても影響を受けません。
高速フレーズや跳躍における指の滑りによる音程ズレ、息の速度や口の形による音程変化などを容易に付加できます。
常に一定にするとただ調律が狂っている楽器のようになってしまうので、フレーズに合わせて変更した方が良いと思われます。
ピッチベンドとは異なり、発音中に値を変更しても効果はないので使い分けが必要です。
これまでSWAMの基本的なパラメータについて、使い方や考え方をご紹介しました。
まだ触れられていないパラメータもあるのですが、次でいよいよ最終回です。
最後までどうぞよろしくお願いいたします。