今回はビブラート表現についてお話しします。
自在なビブラート表現はSWAMシリーズの強みのひとつであり、変化も入力も分かりやすく易しい部類のため、曲に彩りを与えるのにとても効果的です。
ビブラートの正体は音量や音程の変化によるものですが、その仕組みを知ることでより自然な表現に近づけられます。
管楽器と弦楽器ではビブラートの掛け方が異なるため、分けて考えます。
2019.06.06
今回はビブラート表現についてお話しします。
自在なビブラート表現はSWAMシリーズの強みのひとつであり、変化も入力も分かりやすく易しい部類のため、曲に彩りを与えるのにとても効果的です。
ビブラートの正体は音量や音程の変化によるものですが、その仕組みを知ることでより自然な表現に近づけられます。
管楽器と弦楽器ではビブラートの掛け方が異なるため、分けて考えます。
管楽器のビブラートは主に音量の変化によるものですから、Vibrato DepthやVibrato Rateを使わずExpressionグラフを波打たせて表現することもできます。
楽器経験者の方はウィンドシンセサイザーやブレスコントローラーなどを使い、Expressionのみでビブラートを表現した方が自然だと思われますが、その場合はVol.3で触れた「楽器別の感度設定」がとても重要です。
ビブラートは息のダイナミクスによって表現されますから、ダイナミクスが大きくなりやすい楽器ほどビブラートも深く速くなる傾向があります。
ダイナミクスが大きくなる箇所に視点を移してみると、吹き始め、吹き終わり、クレッシェンドやデクレッシェンドなどで深さや速さが変化しやすいとも考えられます。
また、エクスプレッションと同様、一音だけでなく、ビブラートの掛かる音をまとまりで捉えて抑揚をつけることも大切です。
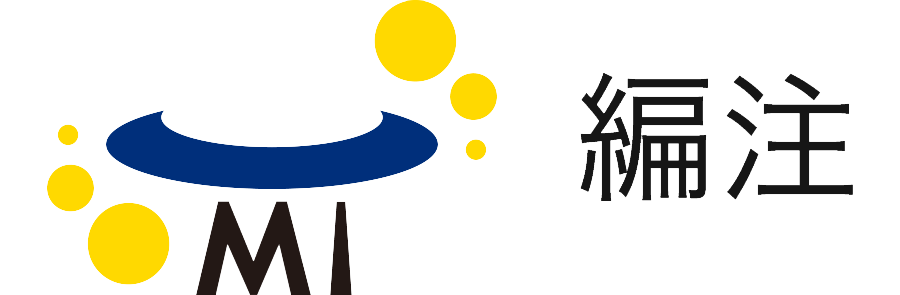 ウィンドシンセサイザー:管楽器と同様の演奏を行なうことでMIDI入力が可能な電子楽器。代表的なものにAKAIのEWIシリーズ、ヤマハのWXシリーズなどが存在する。⇒詳しく(Wikipedia)
ウィンドシンセサイザー:管楽器と同様の演奏を行なうことでMIDI入力が可能な電子楽器。代表的なものにAKAIのEWIシリーズ、ヤマハのWXシリーズなどが存在する。⇒詳しく(Wikipedia)
デモソング:Wavダウンロード(約6MB)
今回のデモソングではビブラート速度のグラフは複雑で参考になりにくいため、一部だけ掲載しています。
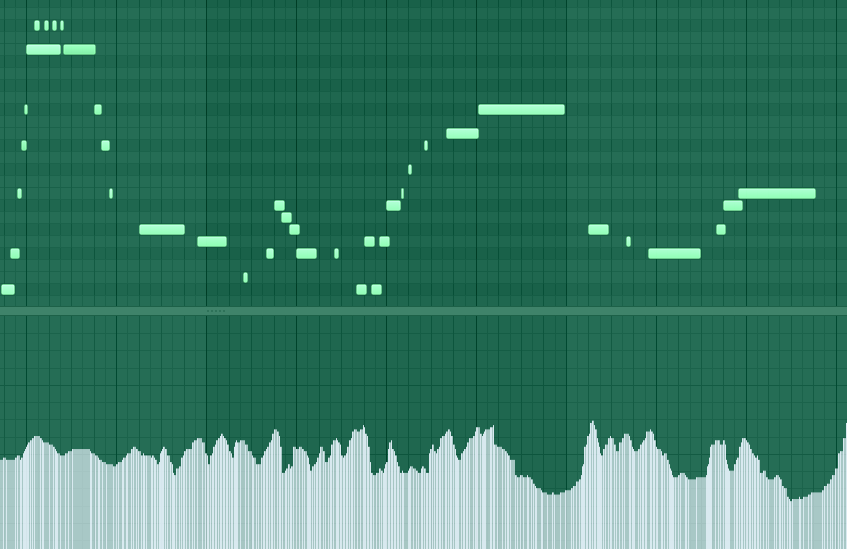
フルート[ビブラート速度]
Leap Motion(3Dモーションセンサー)による入力で、有機的なブレを反映させているためにグラフがガタガタしています。
SWAMにはVibrato Randomというパラメータがあり、ビブラート速度にブレを付加してくれる機能が備わっていますが、常にブレを強くするとかえって機械的になるため注意が必要です。
こういったランダマイズ機能は、速いフレーズやエクスプレッションが減少し不安定になる箇所で部分的に強めると効果的です。
それではビブラート深度のグラフに移ります。
ビブラート部分とノンビブラート部分を分けてメリハリをつけるため、全体的に四角いシルエットになっています。
四角いシルエットから逸脱した部分やフェードなど、単純なオンオフ表現以外の部分に注目していただけたらと思います。
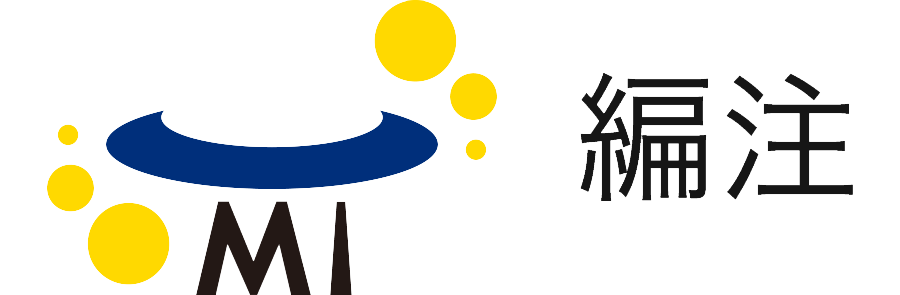 バスーン:英語名はファゴット。オーボエと同様のダブルリード式の木管楽器。吹き口に当たるボーカル(bocal)と呼ばれるパーツを変更することで、音色が変化するのも特徴。⇒詳しく(Wikipedia)
バスーン:英語名はファゴット。オーボエと同様のダブルリード式の木管楽器。吹き口に当たるボーカル(bocal)と呼ばれるパーツを変更することで、音色が変化するのも特徴。⇒詳しく(Wikipedia)
弦のビブラートは主に音程の変化によるものであり、次のような順序で表現します。
つまり、発音からビブラートの発生までに若干の時間差が生じるということです。
SWAM-Sでは、ビブラートの振幅が大きくなる時間をVibrato Fade-In(ms)で設定できます。
最小時間が0ではないため、ノートオン以前から値を設定していても大きな影響はありませんが、 初めと終わりのノンビブラート部分をきちんと表現すると生々しさが増します。
ここで、Vibrato Depthのパラメータを一定にして低音と高音を鳴らした動画をご覧ください。
Vibrato Depthは音程の変化幅(振幅)であることがわかります。
指で振動する弦の長さを調整することで音階を鳴らしているわけですが、音が高くなればなるほど、音階を鳴らすための間隔は短くなっていきます。
すなわち、ハイポジション・細い弦ではビブラートが深く掛かりやすいということです。
高音になればなるほど少し指をずらしただけでも大きく音程が動くため、低音より少ないエネルギーで速く深いビブラートを行えます。予備動作も少なくて済み、ビブラートの立ち上がりも早くなります。
弦楽器のビブラートは主にピッチの変化によるものですから、ピッチベンドの波形を描くだけでも表現できますが、難度は上がりますし修正も大変です。
多くのパラメータを併用すると機械的でないビブラート表現が易しくなります。
Vibrato DepthとMIDIコントローラーの紐付けについて少しお話しします。
私はLeap Motionを使い、左手の動作に6~8種のパラメータを割り当てて同時に制御入力していますが、ただ割り当てただけでは望まないタイミングでビブラートが掛かってしまったりするため、複数同時制御のメリットが得られません。
そこで、パラメータに合わせたマッピングを行います。
画像はVibrato Depthの感度設定グラフです。
デッドゾーン(コントローラーの遊びの部分)をつくり、入力の精度を保てるようにしています。
マッピングカーブは上に凸にし、メリハリのあるビブラート入力ができるようにしています。
DAWやMIDIコントローラーそれぞれの感度設定を組み合わせると、より馴染むようになります。
SWAMシリーズを「演奏する」にあたり、自分に合った感度設定がとても重要です。
Vibrato Rateは周波数で、1秒間に何回振動するか(速さ)を決定するパラメータです。
3.0~9.0と、最低値と最高値では3倍の差があります。
周期はどのように決定されるか、例外はありますが、勢いをつけ力が入りやすい箇所で速まる傾向にあります。
例えばアクセントやクレッシェンド、弓の強い引き離しや弓の返しなどです。
逆に遅くなるのは、弦に弓を乗せたまま緩やかに静かに止める箇所や、跳躍のあるレガートの直前、勢いをつけて周期を速める前です。
ビブラート速度が一定だと機械的な演奏に聴こえやすくなります。
特に長音ではそれが顕著なので、グラフを複雑にするかVibrato Randomを使って均一にならないようにします。
余談ですが、弦楽器で管楽器のような音量の変化によるビブラートを表現しようとすると、(厳密には弓の方向が違いますが)トレモロのようになります。
デモソング:Wavダウンロード(約9MB)
弦のビブラートは主に音程の変化によるものであり、次のような順序で表現します。
バイオリン[ビブラート深度]
Vol.1でお話した、予備動作について思い出していただければと思います。
ローポジション・太い弦では深いビブラートを掛けるために比較的大きな動作を必要とするため、下に凸のグラフを描いてビブラート開始の時間をほんの少し遅らせると自然です。
音域による傾向のほか、ビブラートを意図的に掛けるか掛けないかを一音ごとに判断しています。
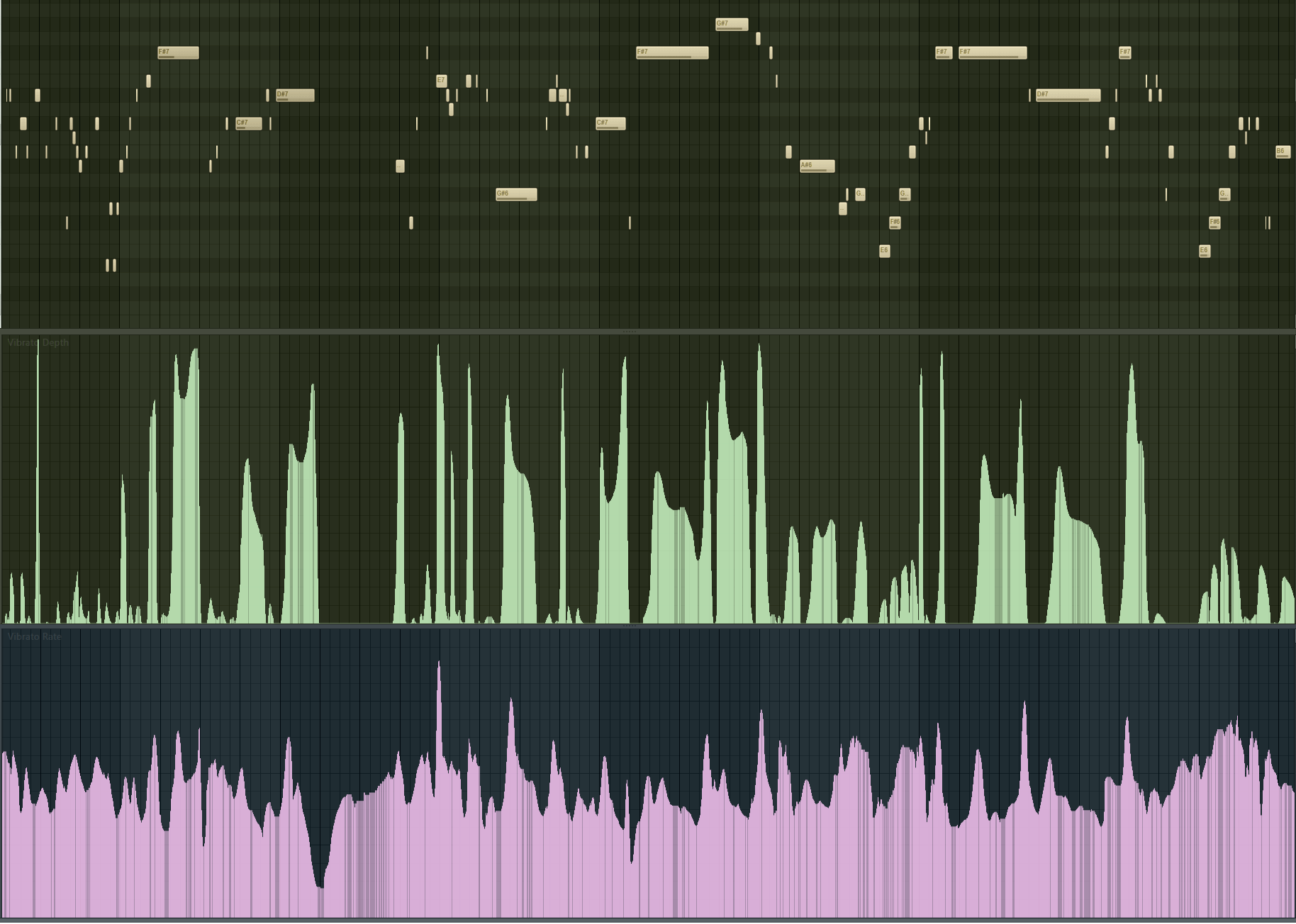
上のグラフがVibrato Depth(ビブラート深度)、下のグラフがVibrato Rate(ビブラート速度)です。
木管楽器と同様、Vibrato Randomの高値を局所的に併用しています。
短い音にも一瞬だけ速く深いビブラートを掛けている箇所があります。グラフで見ると針のように鋭くなっていますね。
ビブラートそのものにも抑揚をつけます。
後半のフレーズのように、大きな山の中に更に音型ごとに小さな山をつくると、ビブラートが連続する箇所でも平坦な印象を与えません。
ビブラートは奏者の癖が分かりやすい表現のひとつです。
今回のデモソングでは、
といった傾向のある奏者をデザインしています。
MIDIでは0~127まで数値入力できますが、SWAMのCCマッピングはデフォルトの上限値が100と設定されています。(MIDI: 127 が入力されたとき Vibrato Depth: 100 になる)

上限値100のままで不自由なく制御演奏できますが、上限値127にすると相対的にコントローラーの感度が下がるので注意が必要です。
指で弦に触れず、そのまま弓で弦を弾く奏法です。
SWAM-SではAlt. Fingering (AltFing): Nut+Open(駒寄り+開放弦)を指定するか、ピッチベンドを極端に下げた場合にのみ演奏可能です。
当然ビブラートは掛けられず、ピッチも比較的安定しています。
重音奏法(ストップ)への組み込みや、ピチカートなどでよく見られる奏法ですね。
SWAMでは開放弦にビブラートの値を設定しても掛からないようになっている(GUIにも反映されます)ため意識しなくても大丈夫ですが、開放弦の響きは豊かで目立ちますから、前後の音とのバランスには気をつける必要があります。
ビブラートが前面に出ている演奏は、よく「情熱的」だと言い表されます。
しかし、ただ単に深く速く掛かっていれば感情を揺さぶる演奏になるかと言うと、そうではありません。ビブラートも抑揚表現の一種と考えられるので、変化量とタイミングが要となります。
音程が揺れるということは、すなわち不安定だということです。
行き過ぎると焦燥感を煽り心地悪さへと繋がってしまいますが、適度な不安定さは人間味を引き立て表現する重要な要素であり、安定と不安定のバランスによって音の印象を変え、感情に訴えるのだと考えられます。
揺れることとパフォーマンス的に揺らすことは違いますが、奏者は最適な音を出すために弾きながら体の位置を細かく調節しています。
SWAMではこの「揺れ」についても設定でき、Pan Behaviorという項目でDyn1,Dyn2,Acoustsic,Balanceの四種から選択可能です。
なお、ここで扱うPan(定位)はSWAMに搭載されているPan Potです。DAWで制御するPanではなく、全く挙動が違うので注意が必要です。
Pan Potを左右どちらかに振ってから確認すると効果が分かりやすいです。
Dyn1,Dyn2では奏者の体の揺れを再現でき、Acoustic, Balanceでは奏者は揺れません。
Balanceのみ、リバーブの発生位置にも影響を及ぼします。(つまり、DAWのPanと同じです。)
まだまだお話したいことが山のようにあるのですが、今回はこの辺で・・・。
次回はいよいよ「音色」に関わるパラメータについてお話ししたいと考えています。