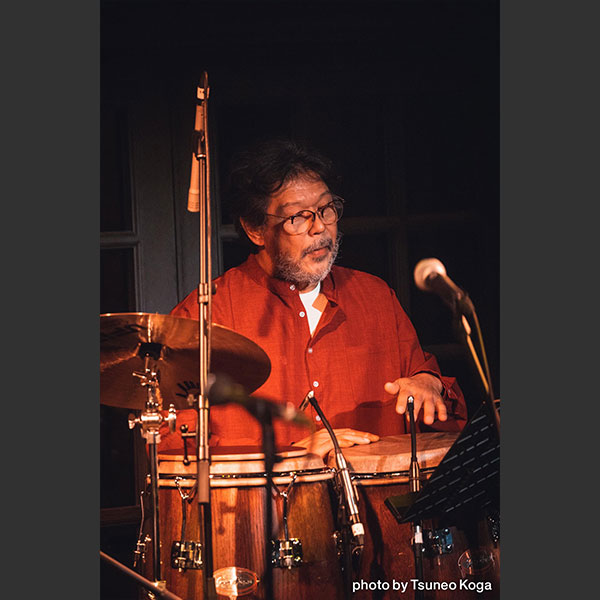- TOP
- Tips / Article
- BLUE NOTE PLACE “Chooses” Earthworks Microphone
BLUE NOTE PLACE “Chooses” Earthworks Microphone
2023.01.25
ブルーノート・ジャパンによる食と音楽を融合させた新たなダイニング「BLUE NOTE PLACE」が2022年末、恵比寿にオープンした。吹き抜け2階建ての解放感あふれるスペースでは、食事を楽しめるだけでなくライブパフォーマンスやDJなども日々行われている。
そんなBLUE NOTE PLACEの新規オープンに合わせて導入されたマイクが、Earthworksのドラム用マイクセットのDK7と、ボーカルマイクのSR40Vだ。プレミアムなライブを楽しめる最高の空間にふさわしいこれらのマイクが選ばれたのはどんな理由からか。ハウス・エンジニアの福原淳人氏と、水戸晃弘氏にお話を伺った。

安心できる、してもらえる
MI
BLUE NOTE PLACEのオープンに合わせ、ドラム用のマイクにEarthworksのDK7、ボーカル用のマイクにSR40Vを導入頂きました。選定や導入に至った経緯などをお聞かせください。
福原 淳人さん(以下、福原)
2022年12月にこのBLUE NOTE PLACEを新店舗として運営するにあたりマイクの選定やテストをしていました。新しく始める場所なので、まずは自分たちが音場を正しく把握する必要がありましたが、スタート時に揃える機材選びはそれ以上に重要な事なので慎重に行いました。
ライブハウスの常設機材なので「壊れにくいこと、使いやすいこと」は必要な要素だし、それから乗り込みのエンジニアさん(アーティストと帯同するエンジニア)に対しても「安心できる、してもらえる」ということが前提条件でした。そうなると、小屋機材はだいたい業界スタンダードなマイクになりますよね。自分達だけが好きなマイクでも仕方ないですし。でも、この小屋の響きを最大限に活かせるハイクオリティなマイクを導入したいという思いもあって、その辺りを天秤にかけて選定した感じです。
以前Blue Note Tokyoで、あるアーティストがEarthworksのマイクを持ってこられていて、その時の印象がすごく良かったんです。Earthworksというブランドなら多くのエンジニアから信頼がある。乗り込みさんがEarthworksを使ったことがなかったとしても、「すごくいいマイクですよ」と僕らが勧められて、実際に使ってもらい「本当だね」と返ってくるような物なら導入の条件は満たしているなと。オープン前に一度Blue Note Tokyoで試してみたいなと思いました。
水戸 晃弘さん(以下、水戸)
そんなタイミングでメディア・インテグレーションの方から試してみないかという連絡をもらって、絶好のタイミングでしたね。試したいなと思ってたまさにそのタイミングでテストすることができたんです。
いかにPAの存在を消せるか
MI
実際にBlue Note Tokyoで試されてみて、いかがでしたか?
水戸
僕自身がモニターを担当した現場で、ドラムキット用のDK7(キック、スネア、タム、トップ用のマイクバンドル)を試させてもらって。福原がマイクを立てながら僕が音を確認し始めて真っ先に「なんだ?これは」と。ただマイクを置いただけなのに、どうしてこんなにいい音が既にできあがっているんだ?と率直に驚きました。
その日のドラマーさんは元々昔からある定番ダイナミックマイクをタムに使うのを一番気に入っていらっしゃったのですが、DK7セット使ってみたところ、「今日は音が本当にいいです、BlueNoteさんこのマイク買った方がいいですよ!」って言われちゃいました(笑)Earthworksはコンデンサーだし、それまで使っていたダイナミックマイクとは全然カラーが違うはずですが、プレイヤー本人が気に入ってくれていることが一番ですからね。

福原
彼(水戸)は色々なドラマーさん各人のこだわりを良く知っていますから。
MI
熟練のミュージシャンにそういった評価をいただけるのは嬉しいですね。今までとは何が違っていたのでしょうか?
水戸
僕の作業としては、ご本人が聞いている位置で音を聞いて、卓に戻ってイヤモニでチェックするということを繰り返すのですが、DK7は「本人の位置で聞いていた音がそのまま鳴ってる」と素直に思いました。その方はライブでは非常に割り切った考え方をされていて、それまでのマイクだとモニターのタムやキックにゲートをかけてしまうことも珍しくなかったのに、DK7でEQは最低限のハイパスだけ。ほとんど「ド」フラットの状態でしたね。
MI
演奏者本人が聴いている音と違いがなければ、一番演りやすいはずですよね。
水戸
そうなんです。だから、それまではEQやダイナミクスで作り込んだ音をモニターに送っていたけど、ちゃんとチューニングが施されたドラムがそのままイヤモニから聞こえていました。余計な処理をしていなくても音が完成しているので、過剰に音量を上げる必要がなかったのもよかったですね。
MI
マイクによるキャラクターを付けず、透明なままに音を捉えるというのは、まさにEarthworksが目指しているポイントです。
水戸
透明度の高いマイクというのは本当に重要で、ミュージシャンが望むならPA側で音をあえて汚したりキャラクターをつけることもできるし、忠実にそのまま出すこともできる。逆はなかなか難しいですから、色がついていないというのが素晴らしいですね。個人的には文句の付け所がないし、これからも使い込んでいきたいマイクだなと思っています。
福原
その日、FOHの方もEQはフラットでした。フュージョンでタムにEQしなかったの初めてかもしれない。位相だけ意識してマイキングをし終え聴いてみたところ良かったんですよね。余計な処理をしないって大事ですから気持ち良くフェーダーをあげました。真横にベースアンプがあり全体ミックス上の低音を締めるためにオーバーヘッドのSR25だけは65Hzあたりから下をシェルビングでカットしたけど本当にそのくらい。ドラム自体チューニングも叩き方も最高だったから、そのまま出てくれるマイクはベストだったんですよね。色付けのないマイクですが楽器の鮮やかさは確実に捉えていました。
MI
Blue Note Tokyoに出演されるミュージシャンの方々は卓越された方々が多いから、ご自身のプレイも楽器のチューニングも素晴らしいですよね。そういった環境にEarthworksは最適ではないかと思っています。
福原
本当にその通りですね。スタンダードマイクの中にはチューニングがどうであろうとそれなりの音で出るマイクもありますが、その音でしか出ないという感じもあるんです。僕らは加工感が強い音は好きではありません。「いかにPAの存在を消せるか」が課題だし、それが一番難しいことかなと思っているので、本当にマイク選びって大事ですよね。
今までの経験とは違うロジック
水戸
Earthworksのマイクは、音が本当に素直でそのままを伝えてくれるので、マイキングが間違っていれば間違った音が出る。だから現場で「わかる」んですよね。だからマイキングの判断も楽になるんじゃないかな。
MI
マイキングの間違いがわかる、という言葉は嬉しいですね。
福原
トップに使ったSR25なんかは本当に1センチづつずらしても変化がわかるし、このマイクは本当に楽しい。キックのSR20LSもすごく秀逸。ホールに突っ込まずフロントヘッドの中心あたりを離して狙ってみたのですが、あんなに生そのままのクリアなバスドラムがライブサウンドで聞けたのは、初めてですね。

水戸
あのキックはすごかったですね。僕も印象深い。
MI
少しラウドな環境などでも同様のクリアさは得られるでしょうか?
水戸
得られると思いますね。実際、ドラマーの前にトランペットやサックスの奏者が並ぶ現場でモニターの音を作ったときも、トップのオーバーヘッドのマイクはほとんど処理せずプレイヤーに返すことができたんです。爆音で管楽器が鳴っている環境でも、自分のプレイがわかるんですね。トップの音を余計に返す必要がないのも最高です。イヤモニでモニターを確認してると、ドラマーの細やかなライドのコントロール具合も聞き取れるほどでした。
福原
指向性の制御が他のメーカーに比べて優れてる印象ですね。鋭いわけじゃないからもちろん他の音も被ってくるんだけど、その被りこんだ音が綺麗なんですよ。
水戸
そうですね。マイクの指向性で起きる特有の「キャンセル感」の具合が全然嫌な音じゃない。今までのマイクを考えると、不思議な感じがします。
MI
そこはEarthworksの特徴の1つです。一般的なマイクは指向性の範囲の端に向かうにつれ高域の特性が落ちていってしまうものですが、Earthworksの場合は指向性の範囲内で特性が変わることがありません。理論値に近い指向特性をもっているんですね。彼らはこれを「ニア・パーフェクト」と呼んでいます。
福原
ライブ環境のミックスって被り込みが当たり前にありますから、その楽器に向けたマイクをその楽器のためだけの音色にするわけにいかない事も多いわけです。ステージ配置の問題もあるので、理想的な位置にマイクが置けるとも限らない。そうなると、そこを補填するためにEQやマイクの本数を調整せざるを得なくなるわけですがEarthworksの場合は被った音を含めても破綻しない。逆をいうと、今までの経験とは違うロジックになってくるので使い込んでみたくもなりますね。
あと、細やかなデザインもよく考えられてると思います。タム/スネア用のDM20は、誤ってスティックで叩かれた時にスティックが「逃げる」ような構造になっていたり、ケーブルが下に向くようにマウントされるとかね。こういうのって我々からすると安心して使える理由とも言えますね。

被り込んだ音も含めて良い音作りができるマイク
MI
ドラム用のDK7の他に、ボーカルマイクのSR40Vも導入いただきました。こちらの印象やエピソードなどはございますか?
福原
あるベテランのシンガーがゲストで登場されるライブがあって、彼はいつも長年使っているマイクを持ってくるけど、その日はゲストだからマイクは任せるとのことだったのでSR40Vを試してもらいました。リハが終わりイヤモニを外したあとマネージャーさんにこっそり「あのマイクどこの?良いね」と話されていたようで、凄く気に入ってくれていたようでした。
水戸
僕はあるバンドでドラマーさんがボーカルも演られるというシーンで使用したのですが、いつもはドラムボーカルさんが歌って「いない」時には目視で確認しながらマイクをミュートする癖をつけています。でもそのライブで、たまたまミュートをし忘れたことがあったんです。し忘れたというか、そのSR40Vに被ったドラムの音が凄く心地のいいルームマイクのように聞こえてて。それくらい、被りの音が本当に綺麗でした。
福原
分かる分かる、僕もボーカルがマイクの前から外れる時は被り込みの差を作りたくなくてフェーダーを2、3db下げる癖が付いてしまっているけど、SR40Vだとそのまんまでいいって思えちゃうよね。
MI
SR40Vはコンデンサーマイクですが、ドラムボーカルに使うという判断はなかなか簡単にできないのでは、とも思ってしまいます。
水戸
そうですね、でもコンデンサーかダイナミックかというよりも、結局は音が最優先なのでやってみたんです。トライ的な意味もあったので、ダメだったら変えようと思って軽く考えてて。結構音量の大きいバンドでしたが、マイクにEQは何もかけないままモニターを上げていったのに、なぜかハウらない(笑)ゲインもばっちり取れているのに。現場で「え?ハウらないんだけどなんで?」なんて話したりして。
福原
真裏側にちょっとだけハイが細く引っ張る箇所があって、EQで切ってもいいけど、オンスタンドで動かないならほんの少しスピーカーかマイクをズラしてあげればOKなんです。そうするともう、本当にフィードバックしない。色々なマイクを使ってきたけど、これは新しい感覚と言えるんじゃないかな。ボーカルにもいいし、管楽器もばっちりでした。生々しさが段違いです。
水戸
信頼できるマイクって、こういうことですよね。
MI
嬉しいコメントです。近年はイヤモニを使うシンガーやミュージシャンの方も増えていると聞きますが、これが広がるとライブサウンドの音の作り方にも変化が起こりそうです。
水戸
そうですね。もちろん今も音質を求めてコンデンサーマイクを使いたいというアーティスト、ミュージシャンの方はたくさんいますが、ステージ上の音量が大きいバンドになると途端にハードルが上がります。コンデンサーマイクでマージンを稼ぎながらモニターに返すというのはなかなか難しくて、あまりコンデンサーマイクの魅力を活かせないことも多々ありました。結局ダイナミックマイクにしちゃうケースもありましたし。
MI
シンガーやミュージシャンからすると、妥協に近い感覚かもしれませんね。
水戸
Earthworksのマイクは、ライブでコンデンサーマイクを使ってクリアーに音を届けたいという方には一度試してもらいたいマイクだと思います。試してみるとまったく違うし、壁を一つ突破した感覚ですね。
福原
今まで「どうやって被り込みを減らすか」というアプローチをしていたけど、どうやってもボーカルマイクに他の楽器は被り込んでしまうわけです。だったら被り込んだ音も含めて良い音作りができるマイクの方がいい。特にイヤモニでクリアーな音を聞きながらライブするシンガーやミュージシャンは被りこみを重要視している。イヤモニで自然な音体験ができるEarthworksのマイクを試してみてほしいですね。
MI
Earthworksのマイクを使って、これから試してみたいジャンルや編成などはありますか?
福原
オーケストラをやりたいですね。コンタクトマイクを使わず遠目に目立たず立てたEarthworksマイクでPAしてみたらどうなるんだろうとは考えます。
MI
まさに先ほどお話しされていた「PAの存在を消す」ができそうですね。
福原
そうですね。ここ(BLUE NOTE PLACE)は壁がレンガなのですが、フラッターがないことと、低域の回り込みがそれほどないのに高音の残響が相対的に長めで音楽的にはリッチでいい響きなんですよ。なのでEarthworksのマイクだったら弦カルテットなんかも録音含め理想的なPAができそうな手応えがありますね。
それから、まだここではやっていませんが、今後の配信ライブを見据えてオーディエンスマイクとしての使い方も楽しみです。Blue Note Tokyoで配信を始めて、オーディエンスマイクがとても重要だなと理解しました。そもそもEQで追い込むものではないし、処理をすればするほど臨場感は失われていく。Earthworksのニア・パーフェクトな特性は、まさに適しているなと思いますね。
BLUE NOTE PLACE Photo Gallery

BLUE NOTE PLACE(ブルーノート・プレイス)
2022年12月6日 恵比寿ガーデンプレイスにオープンした、BLUE NOTE JAPANの新業態ダイニング。200席以上を有する吹き抜け2階建ての開放的な空間で、上質なライブミュージックやDJプレイを、モダンアメリカンの食事とともにカジュアルに楽しめる。
プロフィール

福原 淳人(写真:左)
ブルーノート・ジャパン所属のサウンド・エンジニア
世界中のミュージシャンやエンジニアが集まる環境で貴重な経験を積み、国内外の名だたるアーティストから信頼を得ている。コンサートPAからライヴ・レコーディングまで活躍の幅は広い。
水戸 晃弘(写真:右)
1994年8月8月生 福島県出身。専門学生時代から音楽だけでなくコンテンポラリーダンス・芝居・舞台挨拶など様々なジャンルの現場を経験。2015年ブルーノート・ジャパン入社。